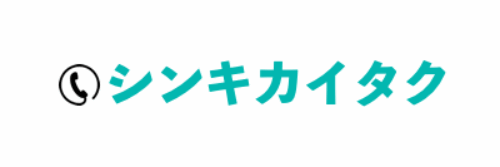テレアポ(電話営業)は、営業活動において見込み顧客と直接接点を持つことができる、極めて有効なアプローチ手法の一つです。しかしその一方で、「断られるのが当たり前」「成果が出にくい」といったネガティブな印象を持たれがちであり、実際に多くの営業担当者が苦手意識を抱えているのも事実です。
本来、テレアポは単なる電話による接触ではなく、戦略的かつ計画的に実施すべきコミュニケーション手法であり、適切な準備と実践的なスキルを習得することで、アポイント獲得率を飛躍的に向上させることが可能です。
本記事では、テレアポの各要素を詳しく解説し、成功率を向上させるための具体的なコツを紹介します。
テレアポの目的とは
テレアポ(テレフォンアポインター)は、単なる「電話営業」ではなく、営業活動全体のプロセスにおける「初期接点の創出」を担う重要な手段です。その主な目的は、見込み顧客(リード)との接点を確保し、商談へと進むためのアポイントメントを獲得することにあります。
具体的には以下のような目的が挙げられます:
1.新規顧客の開拓
既存の接点がない企業・個人に対し、電話を通じてニーズを喚起し、認知・関心高めることで、潜在顧客の獲得を図ります。
2.営業機会の創出
商品・サービスの提案機会を獲得するために、面談・オンラインミーティングなど次のステップにつなげる商談機会を確保します。
3.課題やニーズの把握
テレアポの過程で相手の現状や課題感をヒアリングし、将来的な提案材料とすることも重要な目的の一つです。
4.マーケティング施策との連携
広告やWeb経由で獲得した見込み顧客に対し、テレアポを通じて関係性を深め、コンバージョン率の向上を図るなど、マーケティングとの連携も担います。
テレアポは「即時の売上獲得」よりも、「関係構築の起点」としての役割を果たすことが本来の目的であり、営業プロセスの入口を担う極めて重要な業務といえます。
加えて、テレアポは一過性の活動としてではなく、継続的な営業プロセスの一環として捉えることが重要です。初回の架電において即時に成果が得られないケースも多いため、適切なタイミングでのフォローアップを実施し、段階的に信頼関係を構築していく姿勢が、最終的なアポイント獲得および商談成立へとつながる鍵となります。
インサイドセールスとの違い
近年、非対面型の営業手法が多様化する中で、「テレアポ(電話営業)」と「インサイドセールス」の違いが混同されることが少なくありません。両者は共に顧客と直接会うことなく接点を持つ手法ではありますが、その目的・業務範囲・プロセス設計には明確な違いがありますのでみていきましょう。
テレアポは主に電話を用いて初回アポイントを獲得することを目的とした活動で、営業プロセスの入り口を担う短期的かつ単発的な手法です。一方、インサイドセールスは電話やメール、オンラインツールを活用しながら、見込み顧客と継続的に接点を持ち、商談へとつなげる中長期的な営業活動です。つまり、テレアポが「接点を作る」役割であるのに対し、インサイドセールスは「関係を育てて商談を創出する」役割を担います。
このように、テレアポとインサイドセールスは、似て非なる営業手法といえます。両者の特性を理解し、営業プロセスの中で両者をどう位置づけるかが、成果を左右する鍵となります。
テレアポで追うべき3つの主要目標
テレアポにおける活動目標は、大きく分けて以下の3点に集約されます。それぞれは単独の成果指標であると同時に、営業プロセス全体の中で相互に連動する重要な要素でもあります。
1. 質の高いリードの獲得
単なるアポイント数の追求ではなく、自社の製品・サービスに対して具体的な課題や関心を有する「見込み度の高い顧客」を抽出することが求められます。
たとえば、ITツールを提供する企業であれば、「現在エクセルで業務管理しており、効率化に課題を感じている」といった具体的なニーズが明らかになった場合、それは有望なリードと位置付けられます。
2. 商談機会の創出
テレアポは、直接的な成約を狙うのではなく、次の営業ステップである商談への接続を目的としています。短時間の電話で関心を引き出し、オンラインミーティングや訪問面談のアポイントを獲得することが重要です。
例えば、「一度詳しく話を聞いてみたい」という反応が得られた場合、日時を確定させ、商談の場へとつなげることが成功指標となります。
3. 認知度・想起率の向上
即時のアポイント獲得につながらない場合でも、企業名やサービス内容を伝えることで、将来的な商談機会の土台を築くことができます。
たとえば、「今は必要ないが、半年後に検討したい」「まずは資料が見たい」という回答も、CRMに記録して適切な時期に再アプローチすることで成果に結びつく可能性があります。こうした“種まき”としての活動も、テレアポの重要な役割の一つです。
このように、テレアポは単なるアポイント取得手段ではなく、営業戦略全体における「見込み顧客の選別」「商談創出」「市場浸透」の機能を担うプロセスであると捉えるべきでしょう。
テレアポの手順
テレアポは、単に電話をかけるだけの作業ではなく、営業活動の一環として戦略的に設計・実行されるべきプロセスです。成果を最大化するためには、事前準備から通話中の対応、アポイント取得後の対応に至るまで、各フェーズを体系的に捉える必要があります。
本章では、成果につながるテレアポを実現するための基本的な流れを、各ステップごとに解説していきます。初めてテレアポに取り組む方はもちろん、成果が伸び悩んでいる方にとっても、改善のヒントとなるはずです。
リスト作成
目的:ターゲットとなる企業や担当者情報を収集し、アプローチ先を明確にする。
- 商材のターゲット属性を定義(業種・規模・エリアなど)
- Web検索・企業データベース・展示会出展企業一覧などを活用
- スプレッドシートやSFAに会社名・住所・電話番号・担当部署などを記録
リスト作成においてまず重要なのが、質の高いリスト作成です。ターゲット企業の属性がサービスとマッチしているかを見極めることが極めて重要です。業種・規模・地域といった基本的なセグメントだけでなく、直近の事業動向や経営課題が自社の提供価値と合致しているかも確認すると、通電後の会話がスムーズになります。また、収集する情報は古くなっていることもあるため、公式サイトや直近のプレスリリースなどを活用して最新の情報を確認しながらリスト精度を高めていくと良いでしょう。
スクリプト作成
目的:誰が話してもブレない営業トークを標準化する。
- 自己紹介 → 用件 → ベネフィット提示 → ヒアリング → アポ打診の流れで構成
- 断られたときの切り返しトーク(反論処理)も用意
- トークは読み上げではなく、会話風に自然な文体で
スクリプトを作成する際は、営業担当者自身が読み上げることを前提に、自然な口調と構成を心がける必要があります。売り込み感の強い表現は相手の警戒心を高めてしまうため、課題解決型のトーク構成にすることが効果的です。また、反論対応や切り返しの準備も事前に行い、想定される受け答えに対応できる柔軟な内容にすることで、現場での応対力が向上します。
テレアポや営業トークにおいては、「エレベーターピッチ」「FAB法」「SPIN話法」「ストーリーテリング」など、さまざまなトーク手法が存在します。これらを商材やターゲット、場面に応じて適切に組み合わせることで、より説得力が増し、成果につながる可能性が高まります。
通電(初回架電)
目的:電話がつながるかを確認し、リズムを作る。
- コール数を確保し、10件に1件の通電率を目安に
- 不在時の再架電タイミングも管理
- 受付対応のログも残す
架電業務においては、まず数をしっかりこなすことが基本です。通電率が低い日もあるため、気持ちを切り替えて数を担保しつつ、通電した際には確実に次のアクションに繋げる意識を持つことが重要です。架電ログや通電履歴は再架電時の質を左右するため、相手の反応や通話時間帯なども丁寧に記録しておくと再アプローチの精度が上がります。
受付突破
目的:担当者へ取り次いでもらうための信頼・理由づけを行う。
- 抽象的な表現(例:「ご案内です」)は警戒されやすい
- 受付の方は「味方」にするつもりで丁寧に接する
- 担当者名が分からない場合は部署宛に
BtoBの場合はいかに窓口を突破するかが第一関門になります。受付突破ができない場合、相手に与える第一印象(発声)が問題である場合も多いです。相手に安心感を与え、怪しい電話だと思われるリスクを減らすことも重要になります。
担当者不在時
目的:次回のアプローチに備え、情報を収集し、再架電の準備を整える。
- 担当者の不在を確認したら、戻り予定や対応可能な時間帯を確認する
- 受付の方や他部署からヒントとなる情報を引き出す(例:役職・担当者名・部署名・部署直通番号)
- 「また改めてご連絡させていただきます」と伝え、再架電の計画を立てる。メール送付や伝言を依頼し、接点を残す
担当者が不在の際でも、単に電話を切るのではなく、次の接点を作ることが重要です。受付や窓口対応の方に対しても礼儀正しく接し、「お戻りのお時間帯分かりますでしょうか」「次回どなた様宛てにご連絡するとスムーズでしょうか」といった情報収集をセットで心がけましょう。
また、担当者名が未確認の場合は、部署名や役職、部署直通番号をヒアリングすることで、次回以降の精度を高めることができます。
バイネーム架電(担当者名を把握してかける場合)と、**初回架電(ノンネーム・部署宛など)**では、担当者通電率に大きな差が出るため、後ほど詳細をご紹介します。
担当者通電
目的:アプローチの主目的である「商談の導入」に入る。
- 一方通行にならず、双方向の”対話”を意識
- 相手が忙しい場合は潔く引きつつ再架電約束、情報収集を
- 無理なゴリ押しは印象を悪くするのでNG
担当者に通電しても「今忙しい」「営業は結構です」「メールで送って」などの対応はよくあるケースです。こうした場面では、冒頭3秒で要点を明確に伝え、相手の反応に応じた柔軟な対応が求められます。断られてもすぐに引かず、課題提起や事例紹介を交えて対話を継続することが大切です。また、通話が不成立でも、再架電やメール送付など次の接点を必ず残すことが成果につながります。準備・初動・引き際が通電成功の鍵です。
■ 1. 要件説明
ポイント:冒頭3秒で「誰が・何の目的で」かけているかを明確に。
例:「○○の件でお電話しました、株式会社○○の○○と申します。30秒だけお時間いただけますか?」
切り返し:「今忙しい」→「承知しました。いつ頃がご都合よろしいでしょうか?」
■ 2. 質問(ヒアリング)
ポイント:“課題を聞く”ではなく“共感を呼ぶ問いかけ”にする。
例:「最近○○のようなお悩みって出てきていませんか?」
切り返し:「特に困ってない」→「そうですよね。実は他社様もそうおっしゃっていたのですが、話を聞いて○○の部分で効果を実感いただいてまして…」
■ 3. 商材説明
ポイント:“機能”より“相手にとってのメリット”を端的に伝える。
例:「御社の○○業務を、月10時間削減できるサービスです」
切り返し:「今は検討していない」→「今後のご参考として情報交換させていただきたいです」
クロージング・アポ獲得
目的:訪問・オンライン商談などの日時や具体的な次のステップを決める
- 「どうしますか?」ではなく、具体的にこちらから提案を言い切る
- 資料送付や商談NGに流れないような打ち合わせの意味を持たせるトーク構成(切り返し)
- NGでも記録を残し、追客のチャンスにつなげる
テレアポにおけるクロージングは、これまでの会話を商談という具体的な行動に結びつける重要な局面です。
クロージングの成否は、相手の温度感に応じたアプローチにかかっています。たとえば、相手が関心を示している場合には、迷わずストレートに提案へと進むのが効果的です。
その際に、「それでは、一度詳しくご案内させていただく機会をいただけますでしょうか?」ではなく「それでは、一度詳しくご案内させていただきたいので〇日〇時はいかがでしょうか?」と提案を言い切るのがポイントです。
また、断られた場合でもその場で終わらせず、「また時期を見てご連絡させていただきたいのですが〇〇サービスの切り替えはいつ頃でしょうか?」と、今後の接点を残すことが営業機会の継続に寄与します。押しすぎず、下がりすぎず、相手の反応を的確に見極める姿勢がクロージング成功のカギとなります。
テレアポによるアポイント獲得率を上げるためのポイント
テレアポは「戦略」と「対話力」が成果を左右する営業活動です。
単に電話をかけるだけの作業ではなく、相手の課題や関心を的確に捉え、限られた時間の中で価値を伝えるという、戦略的かつ対話力が求められる営業活動です。
アポイントの獲得率を高めるには、闇雲に架電するのではなく、事前準備からトーク展開、クロージングに至るまで、各フェーズで緻密な設計と工夫が必要です。以下に、成果を上げるために意識すべき主なポイントを紹介します。
1. 断られる理由を自分から作らない
相手に余計な選択肢を与えず、会話の主導権を保つことで、アポイントにつながる確率が高まります。「ご案内だけでも…」「お時間よろしいでしょうか?」といった曖昧な表現は、相手に“断る理由”を与えてしまいます。
断られる理由を自分から作ってしまう言い回しの例
テレアポでは、「断られる理由」を無意識にこちら側が作ってしまっていることが少なくありません。言い回し一つで相手に「断ってもいいんだ」と思わせてしまうと、その瞬間に会話は終わります。営業の主導権は、曖昧な提案ではなく、明確で自信あるトーンにこそ宿ります。言葉選びを見直し、無駄な“逃げ道”を与えない話し方を身につけることで、断られにくく、対話の土台ができる強いトークになります。自信を持って言い切る姿勢こそが、アポ獲得の第一歩です。
2. 理論だけでは突破できない
相手はAIではありません。つまり、ロジックだけだと相手の心が動かないこともあります。感情に訴える言葉やトーンを意識することで、印象がやわらぎ、会話のハードルが下がります。「嬉しい」や、共感ワードの活用は、無意識に相手の警戒を解く効果があります。
テレアポでは、どれだけ理路整然と話しても、相手の心に響かないことは珍しくありません。むしろ、“心地よさ”や“印象の良さ”といった感情的な部分が突破口になることが多いものです。たとえば「嬉しいです」「ありがたいです」「助かります」といったポジティブな感情を表現する言葉は、相手に“感じのいい人”という印象を与え、自然と会話を続けてもらえる空気を生み出します。トークに温度を持たせることで、警戒から共感への転換がスムーズになり、次のステップへつながりやすくなるのです。
ロープレやモニタリングで練習しても良いですね。
3. 相手任せにしないクロージング
「ご都合いかがでしょうか?」では相手に判断を委ねてしまい、アポが流れる原因になります。こちらから明確に提案し、主導的に日程調整を進めることで、確実に次のステップへつなげられます。
せっかく関心を引けても、最後に「ご検討いただければ…」で終わってしまえば、その熱量はすぐに冷めてしまいます。クロージングは押しつけではなく、あくまで“選択肢の提示”であり、“行動を促す提案”です。「いつならご都合よいですか?」よりも「○日○時であればこちらからご説明に伺えます」とこちらが主導することで、相手の意思決定を助けることができます。迷っている相手に、次の一歩を具体的に示すことができれば、アポ獲得の確率は一気に高まります。
4. オープンクエスチョンではなく、クローズドクエスチョンを中心に後から展開する
初対面の電話では、オープンクエスチョン(例:「どのようにお考えですか?」)は負担が大きく、逆に相手の心を閉ざす可能性があります。まずは「はい・いいえ」で答えやすいクローズドクエスチョンで話を進め、徐々に深掘りするのが効果的です。
テレアポにおいては、限られた時間で相手の情報を引き出す必要があります。そのためには、まずは“答えやすい質問”でテンポを作り、相手が話しやすい雰囲気を醸成することが大切です。いきなり「課題は何ですか?」と聞いても、答えに詰まるか警戒されるのがオチです。まずはクローズドクエスチョンで Yes/No をもらい、その流れの中で深掘りをしていくと、スムーズに会話が展開します。聞きたいことを最短距離で引き出すには、聞き方の順序と組み立てがカギを握ります。
初回架電との違いが明確に出るバイネームアプローチ
アウトバウンドコールにおけるバイネーム架電(担当者名を把握してかける場合)と、初回架電(ノンネーム・部署宛など)では、担当者通電率に大きな差が出るのが一般的です。
以下に、実際のBtoB営業現場やコールセンター業界での傾向値・分析ベースをもとにした比較をご紹介します。
■ なぜバイネームの方が通電率が高いのか?
1. 受付突破率が高まる
担当者名をフルネームで伝えると、「何かのご用件だろう」と判断されやすく、取り次ぎされやすくなります。
(例)
✕「人事の方いらっしゃいますか?」
〇「人事部の〇〇様はいらっしゃいますか?」
2. 受付が“選別”しにくくなる
「誰あてか分からない電話」は、営業・セールスと判断されブロックされやすいのに対し、氏名があることで“用件あり”もしくは“取引先かな?”と認識され、対応されやすくなります。
3. 架電担当者側の心理的ハードルも下がる
名前を知っている状態で架電する方が、スクリプトやアプローチが具体化しやすく、成果が出やすくなる傾向があります。
初回架電でも成果を出すためのポイント
- 「次回どなた様あてにご連絡するとスムーズでしょうか?」と伝える
- 「○○のご相談で、関連部署の方につないでいただければ」と明確な目的を提示する
- 受付から名前や部署情報を引き出す姿勢を持つ
→ 初回は情報収集も成果の1つと捉えると、次回のバイネーム架電につなげやすくなります。
まとめ
バイネーム架電は、担当者通電率の面でも、心理的・効率的にも明らかに有利です。初回架電で通電できなかったとしても、担当者名・役職・部署情報を引き出しておくことで、次回からの通電率と突破率が大きく上がります。
効果的なテレアポを実現するためには、戦略的なリスト作成に始まり、相手に響く話し方の工夫、ニーズに即した訴求内容の設計など多角的なスキルが求められます。
加えて、相手の温度感や反応を的確に読み取り、状況に応じた柔軟な応対を行うことも不可欠です。
これらの要素を的確に組み合わせて実践することで、アポ取得の確率を高め、より有望な商談のきっかけを生み出すことが可能になります。さらに、ターゲット選定の精度を高めれば、通電率やアポ率といった成果指標の向上にもつながります。
自社でアウトバウンド営業を導入したいけどリソースが足りない。そのような課題をアウトバウンドセールスの専門家が解決します。

シンキカイタクの仕組み
①貴社のための専属チームを組成
営業戦略コンサルタント、作業の実行部隊、データアナリストの貴社専属チームを組成します。
②最適なターゲットの選定、アピール文言の作成
専任コンサルタントがオンラインでの詳細ヒアリングをもとにターゲットの選定、アピール文言を作成します。
③密なコミュニケーション
貴社の営業部隊として密なコミュニケーションを取りながら営業活動を行います。
④PDCAサイクルの継続
中間・月次MTGにて振り返りを専任コンサルタントと行います。コンサルタントが次月への改善策を提案いたします。
サービス開始までの流れ
- お問い合わせ
- 課題ヒアリング・ご提案
- ご契約・サービス提供開始
- 改善提案・伴走支援
お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームよりご相談ください。ご相談内容を確認したあと、担当者より1営業日以内にご連絡いたします。