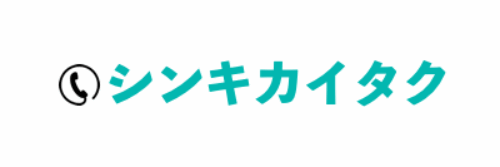「学校へ営業したいけれど、担当教員と連絡が取れない」「話を聞いてもらえない」といった声を、教育機関向けサービスを扱う企業様から多くいただきます。
特に小学校・中学校・高等学校は、日々の授業、校務、部活動、保護者対応など業務が多岐にわたり、スケジュールが読みづらいことから、アポイント取得の難易度が高い領域です。
今回は、そうした小学校・中学校・高等学校に対して、ICT・備品・AI研修・教育サービスなどをより効率的に提案したい企業様向けに、学校営業の実務で活用しやすいポイントをまとめました。
小学校〜高等学校への営業は、大学とは異なり担当者が“教員”であることが多いこと、電話の通りやすい時間帯が限られていること、年度行事によって業務量が大きく変動することなど、独自の特徴が存在します。しかし、相手の状況を理解し、適切なタイミングと営業スタイルを選べば、着実に接点をつくることができます。
学校営業が難しいと言われる理由とは?
小学校・中学校・高等学校への営業は、民間企業や大学とは異なる独自の難しさがあります。
その根本的な理由は「教員の働き方」と「学校という組織の特性」にあります。
担当教員は日々、授業・児童生徒対応・校務・部活動・保護者対応など多岐にわたる役割を担っており、スケジュールを確保すること自体が難しい環境です。ICT担当の教員であっても、必ずしも専任ではなく、授業の合間に対応しているケースが多く見受けられます。
また、学校は突発的な対応が発生しやすい場でもあります。
- 体調不良・怪我など児童の対応
- 保護者からの電話
- クラス運営の急なトラブル
- 行事準備や急な会議
こうした“予定外の業務”が日常的に発生するため、営業側が事前に計画しても想定通りにいかないケースが多くなります。
さらに、企業営業との価値観の違いも難しさの一因です。
学校現場では、
- 生徒の安全
- 教育効果
- 教員の負担軽減
- 保護者に対する説明責任
といった「教育現場ならではの判断軸」が優先されるため、一般的な営業トークだけでは響かない場合があります。
そのため、学校営業では
“相手の忙しさ”と“組織の判断軸”を理解したうえでのアプローチ設計
が欠かせません。
まずは「つながりにくいのが前提」という現場の実情を押さえたうえで、次のステップへ進むことが重要になります。
まず押さえるべき、学校現場の基本構造
小学校・中学校・高等学校への営業では、まず「誰がどの業務を担っているのか」を理解することが重要です。大学と違い、学校現場では導入検討の中心となるのは“教員”であり、校務分掌(役割分担)が大きなポイントになります。
教員が担当者になる理由
小中高では、ICT・備品・教材・研修などの検討を行うのは、多くの場合、以下の立場にあります。
- ICT担当の教員
- 教務主任
- 生徒指導担当
- 教頭(学校運営全体を管理)
大学のように「事務局が一括管理」する形とは異なり、教員が日常業務の合間に判断・準備・検討を行うという構造になっています。そのため、アプローチの成否は“教員の空き時間をどう確保するか”に直結します。
決裁の流れは学校ごとに特徴がある
小中高の導入プロセスは、自治体・学校種別によって異なりますが、おおむね以下の流れになります。
- 担当教員がサービスを認識
- 校内での初期検討(ICT担当・教務など)
- 教頭・校長への共有
- 必要に応じて自治体への申請
- 予算に基づいて導入可否を決定
特に公立学校の場合、自治体(教育委員会)の判断が関わるケースもあり、学校単独で即決できない場合もあります。
学校行事と業務負荷の変動を理解する重要性
学校現場は、年間行事によって業務負荷が大きく変動します。
元の文にもあるように、1〜3月は入試・定期考査・卒業式準備でつながりにくい一方、4〜6月は比較的時間が取りやすく、検討が進みやすい時期です。
- 1〜3月:忙しい(入試・卒業・学年末業務)
- 4〜6月:比較的落ち着く
- 7〜8月:夏休み(検討は進むが電話対応は限定的)
- 9〜10月:運動会・文化祭
- 11〜12月:授業・行事が重なりやすい
このサイクルを理解しているだけで、アプローチの成果は大きく変わります。

学校営業では、「誰が担当者か」「どのような流れで決裁されるか」「どの時期が話しやすいか」を押さえることが、次のステップである“時間帯別のアプローチ設計”につながります。
hotな時間帯で狙い撃ちするアプローチ法
小学校・中学校・高等学校へのアプローチで最も重要なのが、担当教員とつながる“時間帯の見極め”です。学校現場では、授業・校務・保護者対応などが立て続けに発生するため、営業サイドが想定する「隙間時間」が必ずしも相手にとっての余裕時間とは限りません。
そのため、時間帯を外してしまうと、営業トーク以前に「話を聞いてもらえる状態にない」というケースが多く発生します。
電話がつながりやすい時間帯とは
学校によって差はありますが、一般的に授業と授業の間の休憩時間は“非常につながりにくい”傾向があります。教員は休み時間に次の授業準備・配布物の確認・児童生徒対応を行うため、電話対応の優先度が低くなります。
そのため、効果的な時間帯としては以下が挙げられます。
- 午前の職員打ち合わせ終了後
- 給食後〜午後の授業開始までの間
- 放課後(部活がない日や職員会議がない日)
ただし、これらも必ずしも“常に余裕がある”わけではなく、学校現場は突発対応が多いため、柔軟な姿勢が求められます。
「空き時間を聞く」だけでは空振りする理由
元の文章にもある通り、教員の空き時間を聞いてその時間に改めて架電しても、現場では以下のような理由で空振りすることが多くあります。
- 突然の生徒対応
- 保護者からの電話
- 会議・打ち合わせの延長
- 校内調整による予定変更
学校は予定が変わりやすく、多忙な職場であり、事前に把握した時間帯が必ず正確とは限りません。
そのため、“空き時間を聞く→必ずしもつながるとは限らない”という前提を持つことが重要になります。
年間行事と組み合わせたアプローチが効果的
時間帯に加えて、元の文にもあるように、“時期”を踏まえたアプローチはより効果的です。
- 1〜2月は入試関連で忙しい
- 3月は学年末処理・卒業式準備
- 4月は比較的落ち着きやすく導入検討がしやすい
- 9〜10月は運動会・文化祭で電話がつながりにくい
このように、時間帯×学校行事×業務サイクルを重ねて考えると、接点率が大きく改善します。
営業上は泥臭い取り組みに感じられる部分ですが、この「現場に合わせた積み重ね」が、結果的に最も効果的な学校営業につながります。
その為、繋がる時間帯・担当教員の氏名など分析と情報武装を行いながらアプローチしていくことが大切です。
学校営業に求められる営業像とは
小学校・中学校・高等学校への営業では、サービス内容そのものだけでなく、営業担当者の印象やコミュニケーションの取り方が結果を大きく左右します。学校現場では「誠実」「丁寧」「落ち着き」といった要素が非常に重視されるため、営業スタイルもそれに合わせて最適化する必要があります。
元の記事にあるように、学校営業で求められる・アポイントが取れる人物像は
“誠実で若手らしさのある営業担当者”です。
これは単なるイメージではなく、現場の構造から必然的に導かれる傾向でもあります。
教員が安心するコミュニケーションとは
教員は日頃から、児童・生徒・保護者など幅広い層に対して丁寧な対応を求められており、日常的に“信頼される振る舞い”が基準となっています。
そのため、営業にも以下のようなポイントを自然と求める傾向があります。
- 落ち着いた丁寧な説明
- 礼儀正しい言葉遣い
- 過度な営業感を出さない態度
- 相手の状況に配慮した会話運び
いわゆる「押しの強さ」「スピード勝負」といった民間営業のスタイルは、学校現場ではかえって警戒を招く場合があります。

若手らしさ・誠実さが好まれる背景
教員の方々からすると、若手の営業担当者の
- 一生懸命さ
- 素直さ
- 丁寧さ
- 謙虚な姿勢
が“相談しやすい”“対応しやすい”と感じられる場面が多くあります。
これは決して若さそのものではなく、相手にとって“話しやすく安心できる雰囲気”を持っているかという要素が重視されていると言えます。
テレアポ・訪問時に評価されるポイント
学校営業では、初回接点での印象がその後の対応に大きく影響します。
効果的なアプローチとしては、
- 声のトーンを落ち着かせ、ゆっくりめに話す
- 初手から商談色を強めず、情報提供の意図を明確にする
- 相手の時間を尊重し、端的に要点を伝える
- 専門用語を避け、学校現場の視点に合わせた説明をする
などが挙げられます。
多忙であることが前提のため、特にテレアポの場合は短時間で安心感を与えられるコミュニケーションが重要です。
学校営業で成果を出すには、サービス内容と同じくらい「誰が話すか」「どのような話し方をするか」が重要なポイントになります。
学校が抱える課題を理解した提案が成果を生む
小学校・中学校・高等学校では、ICT環境整備から教員の業務負担軽減、生徒指導、保護者対応まで、日常的に多くの課題を抱えています。学校向け営業では、こうした現場の課題を踏まえた“背景理解のある提案”が、導入への大きな後押しになります。
サービスの機能説明だけではなく、学校が抱える問題にどのように寄与するのかを具体的に示すことが求められます。
ICT・備品導入が進む中で表面化している課題
近年はGIGAスクール構想をきっかけにICT化が加速し、学校はさまざまなデジタルツールを導入しています。しかし一方で、以下のような課題も生まれています。
- ICT担当教員の負荷集中
- 導入後の運用・保守に関する不安
- 教員のスキル差による利用のばらつき
- 新しい機器・サービスを使いこなすための時間不足
このように、“導入すること自体”よりも“運用できるかどうか”が不安材料になっているケースが多く見られます。
教員の業務負担を軽減する視点が重要
学校現場では、「導入によって教員の仕事が増えるなら断られる」という明確な傾向があります。
そのため営業では、
- 授業準備がどれだけ簡素化されるか
- 校務がどれだけ効率化されるか
- トラブル時のサポートが十分かどうか
- 教員が追加で覚えることは何か
など、“業務負担の変化”を具体的に提示することが信頼につながります。
学校側が導入後に評価するポイント
学校が実際に導入を決めた際、重視するポイントは以下の通りです。
- 生徒にとってのメリットが明確か
- 教員の業務が合理化されるか
- 学校全体の安全性・安定運用に支障がないか
- 保護者への説明がしやすいか
- 自治体の方針や予算と整合しているか
とくに「保護者への説明のしやすさ」は重要視される傾向があります。
学校は公共性の高い組織であるため、関係者にわかりやすく説明できるサービスほど導入に前向きになりやすいのです。
学校営業では、こうした“学校特有の課題や価値観”を理解し、それに合わせた切り口を提示することで、納得感を高めることができます。
これは企業側にとっても、教育現場と長期的な信頼関係を築くうえで非常に重要な視点です。
学校現場の理解が突破の第一歩
小学校・中学校・高等学校への営業は、教員が多忙でスケジュールが読みづらいことや、学校行事による業務量の変動など、独自の難しさがあります。
しかし、学校の構造や時間帯、年間サイクルを理解したうえで、相手の状況に合わせたアプローチを行うことで、確実に接点をつくることができます。
また、学校現場では「誠実さ」「若手らしい丁寧さ」といった人柄が評価されやすく、過度な営業色よりも、落ち着いたコミュニケーションが信頼構築につながります。
さらに、学校が抱える業務負担やICT導入の課題を正しく理解し、サービスがどのように貢献できるのかを明確に伝えることで、納得感が高まり、導入に向けた議論が前進します。
教育機関向け営業は、単に情報提供をするだけではなく、相手の業務や環境に寄り添った提案が必要です。もし学校へのアプローチに悩まれている場合は、ぜひ一度“教育現場の視点”から営業戦略を見直してみてください。
自社でアウトバウンド営業を導入したいけどリソースが足りない。そのような課題をアウトバウンドセールスの専門家が解決します。

シンキカイタクの仕組み
①貴社のための専属チームを組成
営業戦略コンサルタント、作業の実行部隊、データアナリストの貴社専属チームを組成します。
②最適なターゲットの選定、アピール文言の作成
専任コンサルタントがオンラインでの詳細ヒアリングをもとにターゲットの選定、アピール文言を作成します。
③密なコミュニケーション
貴社の営業部隊として密なコミュニケーションを取りながら営業活動を行います。
④PDCAサイクルの継続
中間・月次MTGにて振り返りを専任コンサルタントと行います。コンサルタントが次月への改善策を提案いたします。
サービス開始までの流れ
- お問い合わせ
- 課題ヒアリング・ご提案
- ご契約・サービス提供開始
- 改善提案・伴走支援
お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームよりご相談ください。ご相談内容を確認したあと、担当者より1営業日以内にご連絡いたします。